七五三はお子さまの健やかな成長を祝う、日本ならではの大切な節目。そんな特別な一日を、プロのカメラマンによる出張撮影で美しく残したいと考えるご家族も多いことでしょう。しかし、撮影場所が「神社」という神聖な場である以上、自由に撮影できるとは限りません。
実際には、神社によって撮影のルールや対応はさまざまで、許可が必要なケースや、撮影自体が禁止されている神社もあります。無許可での撮影によるトラブルを避けるためにも、事前確認とマナーの理解が非常に重要です。
この記事では、「神社での七五三撮影は許可が必要なのか?」という疑問から、許可を取る方法、許可が不要なケース、地域別の撮影NG神社例、そして出張撮影時に守るべきマナーまで、分かりやすく詳しく解説していきます。初めての七五三撮影でも安心して準備が進められるよう、ぜひ参考にしてください。
七五三の神社撮影に許可は必要?

七五三の出張撮影では、神社という「信仰の場」で撮影を行うことになるため、撮影許可が必要な場合が多くあります。特にプロのカメラマンによる撮影や、営利目的での撮影(たとえば撮影サービス業者による出張撮影)は、事前に神社の許可を得るのが基本です。
神社側も、「神聖な儀式が行われる場」としての静けさや秩序を保つ必要があり、参拝者や祈祷中の家族に配慮する観点から、撮影を制限しているケースがあります。そのため、「祈祷を受けた方のみ撮影可」や「境内は撮影OKだが本殿内は禁止」といったように、対応は神社ごとに異なります。
許可を取らずに無断で撮影を行うと、以下のようなトラブルが発生する可能性もあります。
・神社から撮影を中止される
・カメラマンが注意を受け、信頼を損なう
・他の参拝者や神社職員とトラブルになる
・今後その神社での撮影が全面禁止になる可能性も
七五三という晴れの日を、気持ちよく過ごすためにも、事前に神社へ撮影許可を確認することはとても大切です。神社ごとのルールを尊重し、マナーを守った撮影を心がけましょう。
神社での撮影許可を取る方法

七五三の出張撮影を神社で行う際には、事前に撮影許可を取ることが基本です。神社によって対応は異なりますが、共通して大切なのは「マナーを守り、丁寧に問い合わせること」です。
以下で申請の手順や方法について解説します。
1. まずは神社に直接問い合わせる
許可を取るには、まず撮影を希望する神社へ電話やメールで直接問い合わせるのが確実です。最近では、神社の公式サイトに「七五三に関する案内」や「撮影に関する注意事項」を掲載しているところもあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
神社によっては、問い合わせ窓口が「社務所」や「祈祷受付」になっている場合もあるので、連絡時には丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
2. 撮影の詳細を伝えるとスムーズ
許可を得る際には、以下のような情報をあらかじめ用意して伝えると、神社側も対応しやすくなります
・撮影希望日時と時間帯
・撮影人数(家族の人数やカメラマンの有無)
・撮影の目的(七五三の記念撮影など)
・カメラマンの氏名や所属(サービス利用の場合)
とくに七五三シーズン(10月〜11月)は神社が混み合うため、早めの連絡と予約が重要です。
3. 書面の提出が必要な場合も
一部の神社では、特に商業利用(営利目的)やプロのカメラマンによる撮影の場合、申請書の提出や撮影申請書類の提出を求められることがあります。必要な書式は神社によって異なるため、問い合わせ時に確認しましょう。
また、特別な配慮が必要な場合(本殿内での撮影、境内での大規模な撮影など)も、書面による事前申請が求められるケースがあります。
4. 撮影料や祈祷料がかかることも
神社によっては、出張撮影を行う場合に「撮影許可料」や「施設使用料」などの名目で費用が発生する場合があります。また、ご祈祷を受けることを前提に撮影許可を出しているところも多く、「祈祷を受けた方のみ撮影可」という条件がある神社も少なくありません。
そのため、費用が発生する可能性があることを前提に確認・準備をしておくと安心です。
誰が撮影許可を取るべき?親?カメラマン?

七五三の出張撮影を神社で行う場合、「撮影許可は誰が取るべきか?」という点で迷う方は少なくありません。基本的には、撮影を依頼するご家族、つまり親御さんが事前に神社へ連絡し、撮影の可否や条件を確認するのが一般的なマナーです。神社は信仰の場であるため、営利目的や撮影行為について慎重な対応を求めることが多く、親の立場から丁寧に問い合わせることが望まれます。
ただし、出張撮影サービスを利用する場合、一部のカメラマンは撮影許可の確認や申請を代行してくれることもあります。しかし、これはあくまで例外であり、ほとんどのサービスでは「撮影許可は依頼者(家族)側で取得してください」と明記されているのが現状です。
そのため、親が直接神社に問い合わせ、撮影希望日時や目的、人数などを伝えたうえで、撮影可能かどうかを事前に確認することが安心です。また、カメラマンやサービス側に「撮影許可はどちらが取るのか」を事前に確認しておくことで、当日のトラブルを未然に防ぐことができます。
撮影が当日できない、神社に迷惑をかけてしまうといった事態を避けるためにも、撮影許可の取得は「誰が担当するか」を明確にし、余裕をもって準備を進めることが大切です。
撮影許可が不要なケースと注意点

七五三のお参りにあわせて写真を残したいと考える方は多いですが、すべての場合に撮影許可が必要というわけではありません。たとえば、家族だけでスマートフォンや個人のカメラを使って簡単に記念写真を撮る程度であれば、特別な許可が不要な神社がほとんどです。特に境内の一般的なエリアで、他の参拝者の迷惑にならない範囲であれば、問題なく撮影できることが多いでしょう。
ただし、注意すべき点もいくつかあります。たとえば、祈祷中の撮影や、本殿の内部など神聖な場所での撮影は、原則として禁止されている神社が大半です。仮に許可が不要な場所や時間帯であっても、「場所を占有しない」「大声を出さない」「他の参拝者の動線をふさがない」など、常識的なマナーを守ることが大前提です。
また、三脚や照明器具などを使って本格的な撮影を行う場合や、第三者(カメラマン)を同行させる場合は、たとえスマホ撮影でも許可が必要になることもあります。「スマホだからOK」と自己判断せず、気になる場合は事前に神社へ確認しておくと安心です。
七五三はお子さまの大切な節目を祝う行事だからこそ、神社という神聖な場での撮影には配慮が欠かせません。思い出を残すと同時に、周囲への思いやりも忘れずに行動しましょう。
撮影NGの神社例(地域別)

各地域の七五三撮影がNGの神社をまとめました。撮影OKでも許可が必要なケースが多く、申請を忘れると当日撮影できない場合があります。
また情報は変更されることもあるので、撮影希望の神社には必ず事前に最新の確認をしてください。
千葉県の七五三撮影がNGの神社
・千葉神社(千葉市中央区院内)
・諏訪神社(流山市駒木)
・香取神宮(香取市)
・稲毛浅間神社(千葉市稲毛区)
東京都の七五三撮影がNGの神社
・明治神宮(渋谷区)
・花園神社(新宿区)
・新宿十二社熊野神社(新宿区)
・赤城神社(新宿区)
・大鳥神社(目黒区)
・大宮八幡宮(杉並区)
・亀戸天神社(江東区)
・子安神社(八王子市)
・熊野宮(小平市)
・大國魂神社(府中市)
・布多天神社(調布市)
・谷保天満宮 (国立市)
・阿豆佐味天神社(西多摩郡)
神奈川県の七五三撮影がNGの神社
・鶴岡八幡宮(鎌倉市)
・鎌倉宮(鎌倉市)
・亀ヶ池八幡宮(相模原市)
・平塚八幡宮 (平塚市)
・天照皇大神/牛久保神社(横浜市)
・出雲大社相模分祠(秦野市)
埼玉県の七五三撮影がNGの神社
・川口神社(川口市)
・調(つき)神社(さいたま市浦和区)
・金鑚神社(児玉郡)
神社での出張撮影マナー5つ

七五三の出張撮影は、特別な思い出を美しく残せる素晴らしい方法ですが、撮影場所が「神社」であることを忘れてはいけません。神社は参拝者の祈りや神事が行われる「聖なる場所」であり、私たちはその空間に敬意を払って行動する必要があります。
ここでは、神社での出張撮影を気持ちよく行うために、カメラマン・家族ともに意識したい5つの基本マナーをご紹介します。
撮影前に挨拶をする
神社に到着したら、まずは社務所へ行き、撮影の旨を伝えて一言挨拶をしましょう。許可を得ていても、当日の状況によって撮影に配慮が求められることもあります。丁寧な挨拶と報告は、トラブル回避にもつながります。
他の参拝者や神事の妨げにならない
神社は多くの人が訪れる場所です。写真撮影に夢中になるあまり、参拝者の動線をふさいだり、神職の方の業務の邪魔をするような行為は避けましょう。人が少ない時間帯を選ぶなどの配慮も大切です。
三脚や照明の使用は最小限に
本格的な機材を持ち込むと、神社の敷地内では大きなスペースを占有してしまいがちです。特に三脚やストロボなどの大型機材は、通行や視界の妨げになることがあるため、必要最低限にとどめましょう。事前に機材使用の可否も確認しておくと安心です。
撮影エリアを制限する場合は従う
神社によっては「本殿周辺は撮影禁止」「境内の一部のみ可」など、撮影が可能なエリアを指定している場合があります。こうしたルールには必ず従いましょう。無断で立ち入り禁止区域に入っての撮影は、神社との信頼関係を損ないます。
ご祈祷を受ける場合は、先に申し込みをしておく
ご祈祷の撮影を希望する場合は、撮影許可だけでなく、ご祈祷の事前予約も必要です。神社によっては、祈祷中の撮影を全面禁止している場合もあります。事前に内容と流れを確認し、許可が出ている範囲内で撮影しましょう。
まとめ:神社での七五三撮影は、許可とマナーが大切
七五三の出張撮影を神社で行う際は、「撮影が可能かどうか」を事前に確認することが何よりも重要です。神社によって撮影の可否やルールは大きく異なり、「祈祷中のみ撮影OK」や「商用撮影は不可」など、対応はさまざまです。
無許可での撮影は、神社とのトラブルや他の参拝者への迷惑につながる恐れがあるため、必ず早めに確認・申請を行いましょう。特に秋の七五三シーズンは混雑するため、余裕を持っての準備がおすすめです。
また、カメラマンとの事前打ち合わせも満足のいく撮影には欠かせません。どちらが撮影許可を取るか、当日の流れや撮影可能な場所などを事前にすり合わせておくことで、当日もスムーズに撮影が進みます。
「特別な1日」を気持ちよく、そして美しく残すためには、神社への敬意と撮影マナーを大切にすることが鍵です。ルールを守って、思い出深い七五三を迎えましょう。
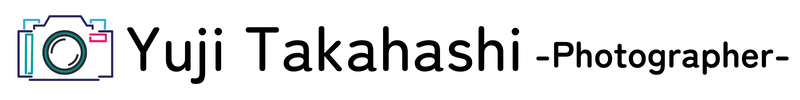
コメント
この記事へのコメントはありません。
この記事へのトラックバックはありません。